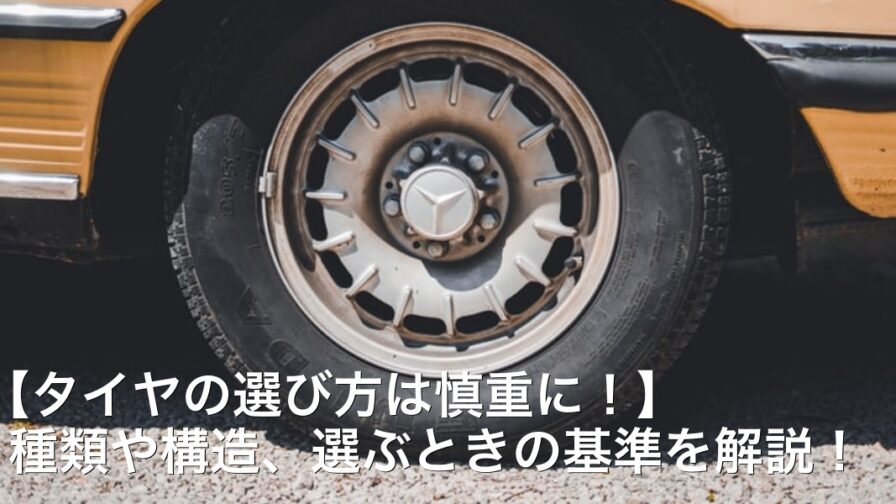車のタイヤを交換・購入する際、
「タイヤ選びの基準は?」
「タイヤによって違いはあるの?」
「タイヤ交換の頻度は?」
この記事はそんな疑問をお持ちの方に向けて書いています。
タイヤの種類は年々増えており、現在ではさまざまな種類のタイヤが市販されています。タイヤの種類を知っておくと選択肢が広がり、より自身の目的に合ったものを選べるようになります。
今回はタイヤの種類や構造、そしてタイヤ選ぶときの基準について紹介します。
2~3分ほどで読めますので、ぜひ最後まで読んで頂けると幸いです。
タイヤの選ぶ方は慎重に!

従来のタイヤは、主にシーズン別に分類されていました。しかし最近では、路面の状況に応じたタイヤが開発され、機能別にも分類別されるほどその種類は豊富になりました。
どのような種類のタイヤが販売されているのか、シーズン別・機能別にみていきます。
シーズン別の分類
シーズン別タイヤの分類は下記に3種類です。
・スタッドレスタイヤ
・オールシーズンタイヤ
タイヤをシーズン別に分けた場合、「サマータイヤ」と「スタッドレスタイヤ」があるのはご存知の人も多いかと思いますが、加えて「オールシーズンタイヤ」を出しているタイヤメーカーも増えており、シーズン別タイヤとはこれら3種類のことを指しています。
それぞれタイヤについて、それぞれ詳しく解説していきます。
サマータイヤ(夏用)
「サマータイヤ」とは、普通のタイヤ(ノーマルタイヤ)のことを指します。冬用タイヤと区別するために、サマータイヤと呼ばれるようになりました。
サマータイヤという名前ですが、夏限定のタイヤではないので、降雪がない地域では年間通して利用することが可能です。一般的に、タイヤはドライ性能や耐摩耗性、乗り心地といった性能が求められています。
サマータイヤは、通常の路面を安全に走行できるよう特定の性能に偏らず、バランスの取れたタイヤです。
スタッドレスタイヤ
「スタッドレスタイヤ」とは、冬用タイヤのことを指します。
雪道を走ることを想定して作られているスタッドレスタイヤで、普通のタイヤよりも柔らかいゴムが使用されています。雪には強いですが、濡れた地面には弱く、スリップする場合があるので注意が必要です。
タイヤがスタッドレスタイヤかどうかを知りたい場合は、側面をチェックしてみてください。スタッドレスタイヤの場合、「STUDLESS」という刻印を確認できます。
また、接地面を見るとギザギザした模様が入っているのでそれもスタッドレスタイヤの証拠です。
スタッドレスタイヤの特徴として、タイヤの回転方向が決まっているタイヤが多いです。ですので、タイヤの履き替えやローテーションをする際は注意が必要です。
オールシーズンタイヤ
「オールシーズンタイヤ」とは、サマータイヤとスタッドレスタイヤの中間にあたる性能を持つタイヤです。
オールシーズンタイヤは、真夏の乾燥路から軽い雪道までの走行に対応しています。
季節の変わり目に交換する必要がなくオールシーズンに使えて便利なタイヤですが、サマータイヤよりも燃費性能が低く、スタッドレスタイヤよりも走行可能な雪道は限定されてしまいます。
オールシーズンタイヤはスタッドレスタイヤよりも雪に弱いので、降雪地域で年中「オールシーズンタイヤ」の使用は難しいです。年に2~3回程度降雪する地域に適しています。
オールシーズンタイヤは少し中途半端な面があります。
機能別の分類
機能別で見ると以下8種類のタイヤがあります。
・マッドテレーンタイヤ
・エコタイヤ
・シーリングタイヤ
・ランフラットタイヤ
・コンフォートタイヤ
・スポーツタイヤ
・応急タイヤ
それぞれ具体的にどのような機能があるのか紹介していきます。
オールテレーンタイヤ
「オールテレーンタイヤ」とは、舗装された道路だけでなく、砂利道や泥道といった悪路も走破できるタイヤです。ゴツゴツとしたタイヤになっており、剛性とグリップ性に優れ、オフロードを走行する機会のある車によく装着されています。
オールテレーンタイヤは、オンロードとオフロードの両方に対応していますが、燃費性能はオンロード用のタイヤに比べて悪いです。
また、凍結路面は苦手で、雪道の走行はスタッドレスタイヤよりも滑りますので走行はしないようにしてください。
マッドテレーンタイヤ
「マッドテレーンタイヤ」は、オールテレーンタイヤの「オフロードを走るための性能」をより高性能にしたタイヤです。オフロード性能とオンロード性能が両立されていますが、よりオールテレーンタイヤよりもオフロード向きなタイヤです。
オフロードレースに参加する方やアウトドアレジャーでオフロードを走行する機会が多い方など、オフロード走行を重視する方には向いています。
また、マッドテレーンタイヤはオフロード走行重視のため、タイヤのノイズが大きく、燃費は通常のタイヤより悪いです。
エコタイヤ
「エコタイヤ(低燃費タイヤ)」とは、燃費性能に優れたタイヤのことを指します。
転がり抵抗を低く抑え、タイヤが回転しやすいように設計されています。燃費性能を上げるため、ほかのタイヤよりも軽量となっています。
転がり抵抗が低くなると、グリップが低下しやすいです。
しかし、エコタイヤとして市販されているものはグレーディングシステム(タイヤの性能を等級に分けて評価する制度)によってd以上と判断されたもので、ウェットグリップ性能が保証されています。
グリップ力が低下しやすいのは事実ですが、運転する際にそこまで支障は出ません。
シーリングタイヤ
「シールングタイヤ」はご存知ない人も多いかと思いますが、異物が刺さった場合でも走行可能なタイヤです。
通常のタイヤは鋭利な異物が刺さると空気圧が低下したり、パンクする恐れがありますが、シーリングタイヤは内部に粘り気のあるシール材が塗られており、刺さった異物に粘りつくことで空気圧の低下を防ぎます。
たとえ異物が取れたとしても、シール材が穴を塞いでくれます。
ただし、直径5mm以下の穴のみで、5mm以上は対応不可です。
ランフラットタイヤ
「ランフラットタイヤ」はシーリングタイヤと似たような特徴を持つタイヤです。高い剛性を持っており、パンクなどで空気圧がゼロになったとしても最低限の構造を維持することで車の走行を可能にします。
JAFによると、ランフラットタイヤはパンクしてから時速80kmでおよそ80km走行できるそうです。通常のタイヤでパンクした場合、タイヤ交換やJAFを呼ぶなどで対応する必要がありますが、このタイヤであればその必要もありません。
ランフラットタイヤを装着するには専用ホイールが必要で、ほかのタイヤよりも価格が高めです。
コンフォートタイヤ
「コンフォートタイヤ」とは、別名「プレミアムタイヤ」とも呼ばれているタイヤで、乗り心地の良さを追求したタイヤのことを指します。
静寂性と操縦性に優れています。
価格は少し高めですが、燃費性能を備えたものも多く、トータルで考えるとコスパは良いです。
スポーツタイヤ
「スポーツタイヤ」とはスポーツカー向けに設計されたタイヤを指します。
特徴はグリップ力と走行性能の高さで、「走り」や「テクニック」を追求したいドライバーに人気です。
ただし、燃費性能や静寂性などは他のタイヤに劣ります。
応急タイヤ
「応急タイヤ」とは緊急時に使用するタイヤのことで、スペアタイヤとほぼ同じ意味で用いられています。
普通のタイヤと比べてやや小さく、幅が狭いのが特徴です。
最近は応急タイヤの代わりに修理キッドを装備している車が増え、応急タイヤの需要は減っています。
タイヤ構造の違い

タイヤの構造には大きく分けて下記の2つがあります。
・バイアス構造
ここからは、各タイヤの構造の違いについて解説していきます。
ラジアル構造とバイアス構造の違い
ラジアル構造とバイアス構造の大きな違いは、タイヤの骨組みであるカーカス(カーカスコード)の配列です。
カーカスとは、全体の形を決定するタイヤの骨組みで、「衝撃や荷重、空気圧に耐えるパーツ」のことです。
ラジアル構造のカーカスは中心から放射状に配列されていますが、バイアス構造のカーカスは、斜めに並べられています。
ラジアル構造はトレッド部の剛性、耐摩耗性や操縦安定性に優れています。一方、バイアス構造、耐久性や耐衝撃性に優れています。
現在、多くの車はラジアル構造のタイヤを使用しています。応急タイヤなどではバイアス構造が採用されることが多いです。
タイヤを選ぶ時の基準
これまでタイヤの種類や構造を見てきましたが、種類がたくさんありすぎて迷うかもしれません。
タイヤを選ぶ際は下記のポイントを確認することが大切です。
・静寂性
・ドライ性能
・ウェット性能
・耐摩耗性能
それぞれのタイヤ性能について解説していきます。
燃費性能
「燃費性能」とは、走行距離に対する燃費の効率のことです。
燃費性能の良いタイヤとして挙げられるのが、エコタイヤ(低燃費タイヤ)です。JATMA(一般社団法人 日本自動車タイヤ協会)による等級制度と低燃費タイヤを保証するロゴマークが表示されているので、燃費性能の高いものを選ぶ時に参考になります。
ただし、エコタイヤの場合は、グリップ力の低下が懸念されるので少し注意が必要です。
静寂性
「静寂性」とは、走行中に生じる走行音を抑え、静かで快適にドライブできる性能のことを指します。
静寂性は、乗り心地の良し悪しを知る目安にもなります。
小さな凹凸でも気になる人や、運転中のロードノイズを減少させたい人は、静寂性を基準にタイヤを選ぶと良いでしょう。
ドライ性能
「ドライ性能」とは、乾いた路面におけるグリップ力のことです。
ドライ性能が高いタイヤは、ハンドリングが安定しブレーキが効きやすくなります。
ハンドリングのしやすさや、高速道路を走る際の安定性などを求める場合は、ドライ性能に優れたタイヤを選ぶようにしましょう。
ウェット性能
「ウェット性能」とは、雨などで濡れた路面でも安定性を確保しながら走行できる性能のことをいいます。
濡れた路面では、路面とタイヤの間に雨水が入り込み、車はスリップしやすい状態になります。この時、タイヤのグリップ力が低下し、ハイドロプレーニング現象(濡れた路面上で車のコントロールができなくなる現象)を引き起こす可能性が高くなります。
雨天時のドライブが気になったり、濡れた道路を走る機会が多い場合は、要チェックです。
耐摩耗性能
「耐摩耗性能」とは、摩耗しにくい性能のことです。
タイヤは使い続けていくうちに磨耗し、磨耗すると残りの溝が浅くなり、ドライ性能やウェット性能が低下していきます。耐摩耗性能が高いタイヤは、そうでないタイヤよりも寿命が長いという特徴があります。
タイヤをできるだけ長持ちさせたい人や、長い距離を走行する人は、耐摩耗性能に優れたタイヤを選ぶと良いです。
タイヤの交換目安

下記の3項目いずれかに該当する場合は、速やかにタイヤ交換するようにしましょう。
・使用開始から4~5年
・溝が「スリップサイン」に達した場合
それぞれ解説していきます。
走行距離4万km
一般にタイヤは4万kmの走行距離に耐えうると考えられています。
目安として5,000kmの走行で1mmほどタイヤが摩耗すると言われています。
ただし、使用環境などによっても摩耗の具合は変わってきます。
使用開始から4~5年
一般に、タイヤの寿命は最長でも製造から10年程度が目安とされていますが、タイヤメーカーは使用開始後4~5年での交換を推奨しています。
たとえ溝が十分にあり、ひび割れが無かったとしても、さまざまな要因によって目に見えないゴムの劣化が進行している場合もあります。
最低でも、使用開始から4~5年でタイヤ交換するようにしましょう。
溝が「スリップサイン」に達した場合
タイヤの溝の深さには法定基準があり、「いずれの部分においても1.6mm以上」と道路運送車両法の保安基準により定められています。その深さがどこか一部でも1.6mm未満になったものは整備不良として、車検が通りません。
摩耗の程度は「スリップサイン」と呼ばれる箇所を確認することによって知ることができます。
スリップサインのチェック方法
タイヤの側面に描かれた三角マーク(△印)の延長線上にある溝の奥に、ゴムが盛り上がった部分があります。これが「スリップサイン」です。スリップサインはタイヤの全周に複数あります。
どこか1ヶ所でもスリップサインが浮き出た場合は、タイヤの溝が1.6mm未満にすり減ったことを意味します。この状態が、一刻も早くタイヤを交換すべきタイミングです。
実際には、タイヤの残り溝が3mm程度で、タイヤのグリップ力は極度に落ち込み、制動距離が大きく伸びます。ですので、車を安全に走らせるために溝が3mm程度になったタイミングでタイヤを交換するようにしましょう。
まとめ

- タイヤには8つの種類がある
- タイヤはラジアル構造とバイアス構造
- タイヤ選びは各性能をチェック
- タイヤ交換目安は3項目をチェック
今回は、タイヤの種類や構造、選ぶ時の基準、タイヤ交換目安について解説しました。
タイヤにはたくさんの種類があり、迷うかもしれません。ですが、自身のライフスタイルを考え、どの性能を重視するかで、目的に合ったタイヤに絞ることができます。
もし分からない場合は、タイヤを購入する店舗に相談するのも1つの手です。
併せて、自身の車の【タイヤサイズ確認方法】については下記参照ください。
→【プラドのタイヤサイズは!?】タイヤサイズや製造年の確認方法を紹介!